知っていると作品を見るのがもっと楽しくなる アートの材質・技法【写真編】


美術館だけでなく、芸術祭やアートフェスティバルなどのイベントでも楽しむことができる「現代アート」。でも、中には「どうしてこれがアートなの?」と思ってしまうような作品もあるのではないでしょうか?
「現代アートって何?」「どうやって見たらいいの?」「どうしてこの作品がすごいの?」そんな疑問を持ち始めた時に、専門用語などを知らなくても理解しやすく、分量的にも読みやすい、初心者にもオススメの書籍を、シチュエーション別に5冊ご紹介します。
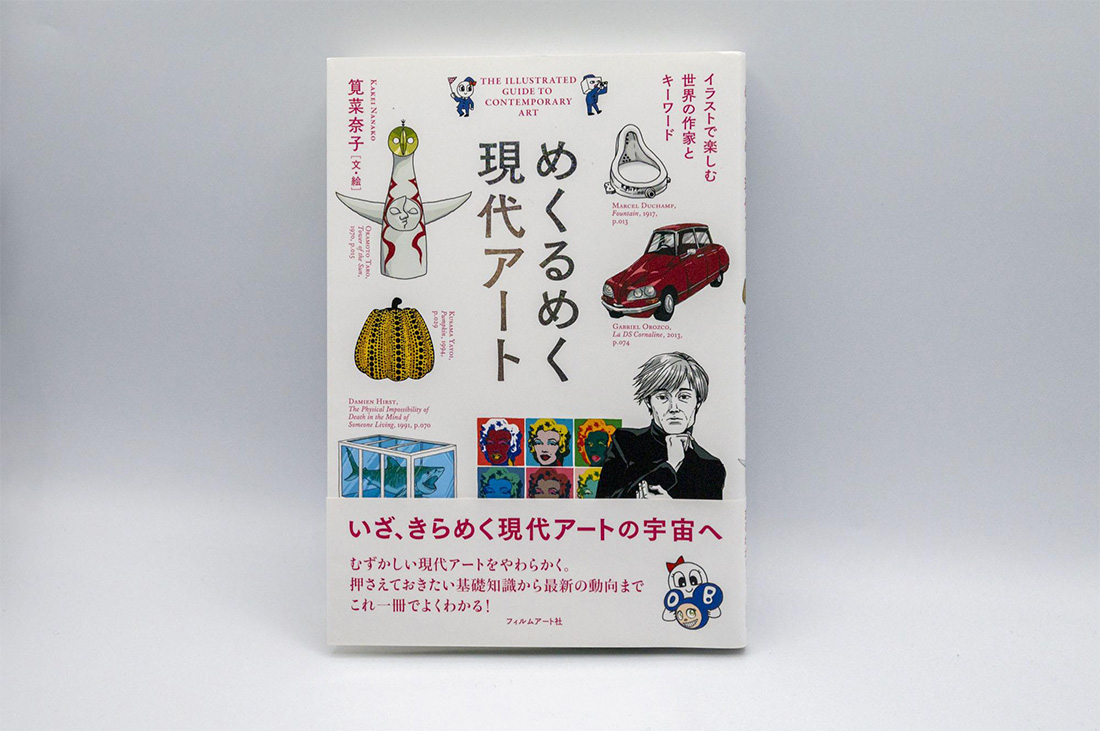
アンディ・ウォーホルやゲルハルト・リヒター、クリスチャン・ボルタンスキー、ヨーゼフ・ボイス…など、名前は聞いたことがあるけれど、どんな作品があって、どうして有名なのかをまずは簡単に知りたい!という方にオススメです。
現代アート分野で有名な「アーティスト」やその「作品」、そして、それらの何が革新的だったのかを簡潔に解説した本です。見開き1ページに1アーティストずつ、たくさんのイラストとともに解説されているので気軽に読むことができます。
イラスト解説なので、文章だけだと頭に入りづらい場合にも、直感的に理解しやすいのではないかと思います。
また、「抽象表現主義」「ポップアート」といったジャンルや、「サイト・スペシフィック」「メディウム」のような、日常では耳慣れない言葉も、さまざまな事例を交えながら解説。「あのアーティストの作品の特徴って何?」「あの言葉ってどんな意味だっけ?」と、気になったときに辞書のようにも使えます。
めくるめく現代アート イラストで楽しむ世界の作家とキーワード / 筧菜奈子
出版社 : フィルムアート社
発売日 : 2016/2/18
言語 : 日本語
単行本 : 160ページ
寸法 : 15 x 1.6 x 21 cm
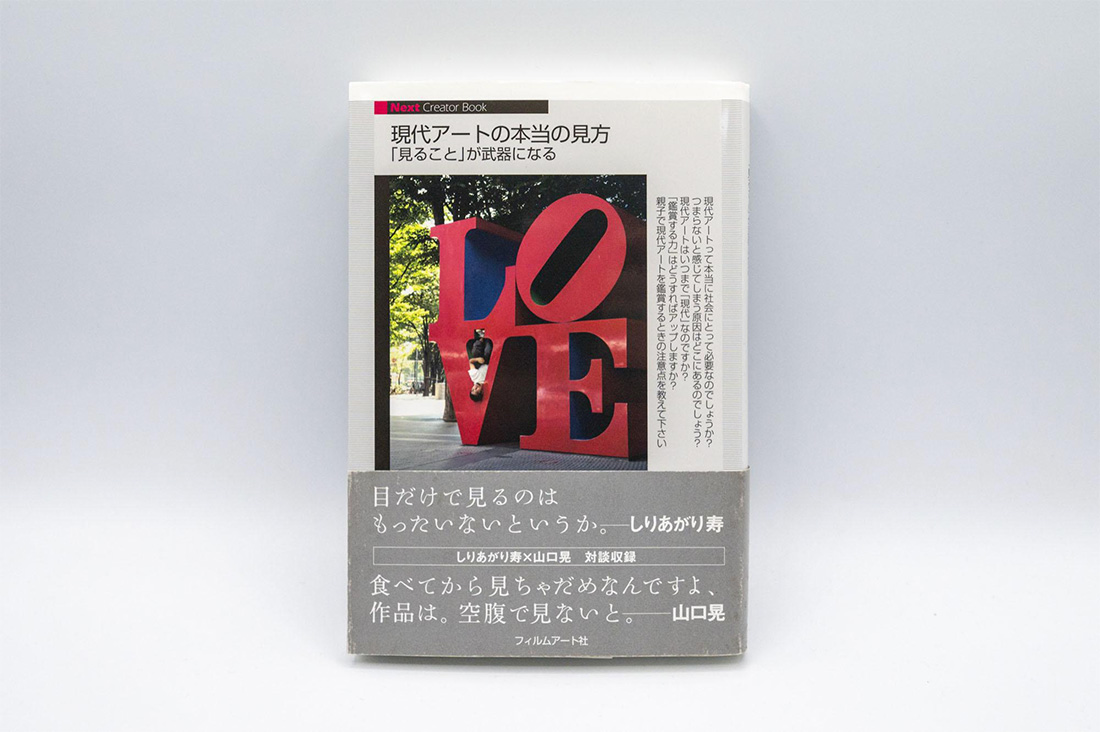
現代アートの作品を見るのは楽しいけれど、作品を見て「面白い」「つまらない」以上の感想をうまく言えない…作品が良かった / 良くなかった理由を自分の中で整理できたらいいのになぁ…と思っている方にオススメです。
現代アートを「どう見るのか?」という点にスポットを当てた本です。
「技術を見る」「社会を見る」「精神を見る」「スタイル別『現代アート』の見方」と、作品を見るための様々な”視点”を紹介しています。こうした視点を知ることで、作品を見るときにこれらを組み合わせ、どんな作品なのかを自分の言葉で説明できるようになり、そこから、なぜ面白い/つまらないと思うのか、読む以前よりも深く考えられるようになります。
内容は、アーティストや批評家、学芸員など、様々なかたちでアートに携わる方々による執筆やインタビューで構成されています。さまざまな立場の方の文章が混ざるので、読みづらく感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、バラエティに富んだ内容は、雑誌のような感覚で読むことができます。
ちなみに「見ることに関する9の質問」という9つのコラムには、「現代アートはいつまで現代なのですか?」「現代アートって本当に社会にとって必要なのでしょうか?」といった、素朴でなかなか聞きづらい現代アートについての疑問についても回答されているのも嬉しいです。
現代アートの本当の見方 「見ること」が武器になる / フィルムアート社編集部
出版社 : フィルムアート社
発売日 : 2014/9/30
言語 : 日本語
単行本 : 208ページ
寸法 : 13 x 1.6 x 18.9 cm

「現代アートの作品が何億円もの価格で取引されるのか理解出来ない…」と疑問に思っている方、もしくは「日本の現代アートは好きだけれど、海外の現代アートは面白さがよく分からない…」なんて思っている方ににオススメしたい本です。
なぜ、これまで日本人アーティストは、片手で数えるほどしか世界で通用しなかったのか?それは「欧米の芸術の世界のルールをふまえていなかったから」。
それでは、どうやって自分の作品の価値を高めていったら良いのか?と、トップアーティストである村上隆氏がご自身で試行錯誤しながら発見し、実戦しながら世界的なアーティストになっていった方法を公開しています。2000年代に出版された本ですが、今読んでも参考になる内容が多いのではないでしょうか。
作品を制作する人に対しての指南書、もしくはビジネス書のように読むことも出来ますが、欧米の芸術に対する基本姿勢や、欧米の作品の暗黙のルールなども説明されおり、そんな前提を知るだけで、海外の現代アートの作品もぐっと理解しやすくなるかもしれません。作品を見る側にも役に立つ本です。
また、作品の価格についても触れられており、なぜ現代アート作品がそんなに高額で売れるのか?という素朴な疑問もクリアになるのではないでしょうか。(ちなみに、村上隆氏は、自分の作品は1億円でも決して高くない!と本書の中で書かれています。そんな理由も気になったらぜひ読んでみてください。)
芸術起業論 / 村上隆
出版社 : 幻冬舎
発売日 : 2018/12/6
言語 : 日本語
文庫 : 230ページ
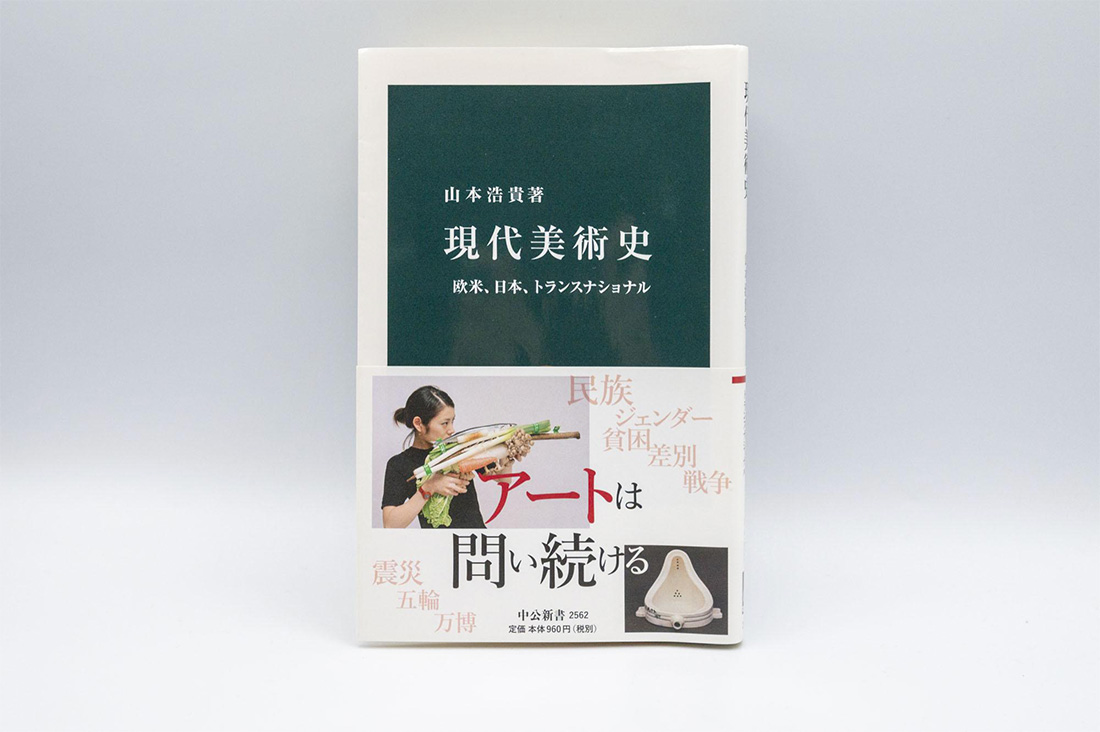
トピックをつまみ食い的に読むよりも、まずは現代美術の流れをひととおり理解したい方にオススメです。また、2000年代以降も含む、現在進行形でアートの世界で起こっていることに興味のある方にもオススメ。
1960年代以降の欧米と日本を中心に「芸術と社会」というテーマに沿って現代美術の歴史を眺める本です。くだけた文体ではありませんが、いきなり専門用語がとび出すこともなく、丁寧に読みやすい文章で書かれています。
アーティストや批評家の固有名詞が多く登場し、聞いたことがない名前が並ぶと若干難しく感じるかもしれませんが、まずは一通り読み進めてみることでざっくりとした流れや動向について知ることができます。
また、例えば「パブリック・アート」のようなアートに関する言葉そのものの意味を知るだけでなく、なぜそうした作品・ジャンルが生まれてきたのかを、アート界の大きな流れから理解できるのも本書の面白いところです。
2000年代以降の動きについても詳細に触れられているのも本書の特徴。展覧会や芸術祭で最新のアート作品を観ているけれど、もう一段踏み込んでその意味を理解したいというときにも役立ちます。なかには、過激で「これがアートなの?」と、衝撃を受けるような作品やムーブメントもあるかもしれませんが、現在進行形の問題に対して、現代アートがどのような応答をしているのかを知ることができる点でもオススメです。
現代美術史-欧米、日本、トランスナショナル / 山本 浩貴
出版社 : 中央公論新社
発売日 : 2019/10/16
言語 : 日本語
新書 : 318ページ
寸法 : 11 x 1.4 x 17.4 cm
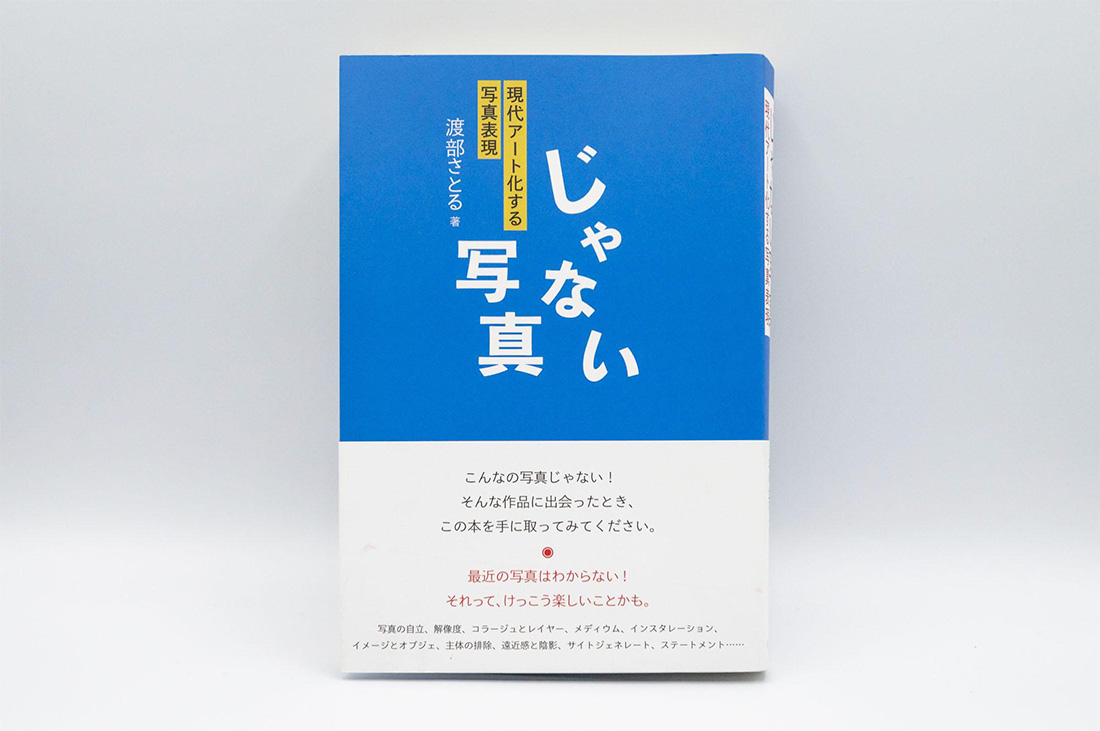
写真は好きだけれど、美術館や写真賞で評価されている”現代の”写真作品の良さ / 面白さがよく分からない、どうやって見たら良いのか知りたい、という方にオススメです。
現代アートのなかでも写真のジャンルに特化した本です。「記録」でもない、「決定的瞬間」でもない、「伝える道具」でもない「現代写真」をどのように観たら良いのかを、写真家の渡部さとる氏が丁寧に解説しています。
「現代写真って何だ?」というコラムと、ご自身の40年にわたるカメラマン・写真家・作家としての体験談を日本国内の写真の流れとあわせて紹介する2章立てで構成。コラムでは、戦後のアートと写真の流れを紹介しながら、有名な現代写真のアーティストたちの作品は何が革新的だったのか、また、なぜ写真作品が高額で取引されるのか、といった理由についても考察しています。
タイトルの「じゃない写真」とは、渡部氏が、これまでに自身で思っていた「良い写真」ではないものがここ数年で写真界で主流になってきていると感じた、今までの写真の捉え方では「こんなの写真じゃない」と思ってしまいそうな写真のこと。もし写真に対してそんなモヤモヤ感を感じることがあったら、ぜひ一度読んでみてください。
ちなみに、「現代写真」の本は読みづらく、写真家として長いキャリアのある渡部氏ですら最後まで読み切れないものも多かった経験から、本書は「楽しんで読めることを目指した」ということもあり、本当に読みやすいです。かたい文や長文は読み切る自信がない…という方にもオススメします。
じゃない写真:現代アート化する写真表現 / 渡部さとる
出版社 : 梓出版社
発売日 : 2020/1/24
言語 : 日本語
単行本(ソフトカバー) : 314ページ
寸法 : 18.8 x 12.8 x 21 cm
筆者がこれまでに読んできた中で、読みやすく、作品を鑑賞するのに「ためになった!」と思う現代アートのオススメ書籍を5冊ご紹介しました。ただ作品を見るだけでも「面白い」「楽しい」「好き」と思う作品も、背景や文脈が分かればもっと楽しくなりますよね。気になる本があったら、是非手に取ってみてくださいね。
文・写真:ぷらいまり。