知っていると作品を見るのがもっと楽しくなる アートの材質・技法【写真編】


史上最大規模の「岡本太郎展」が全国を巡回中です。
展覧会を見て、「もっと岡本太郎の作品を見てみたい」「レプリカではなく、実物の大きなパブリックアート作品を見てみたい」と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか?
生前、芸術が一部の金持ちやコレクターのものとなって秘匿されてしまうのを嫌い、民衆のためのものとしてあることを望んだ岡本太郎。その作品は、美術館やパブリックアートで、いつでも見ることができるんです。
この記事では、岡本太郎の作品をもっと生で楽しみたい方のために、【都内】で岡本太郎の作品が見られる場所をご紹介します。

「岡本太郎記念館」は、表参道の駅から徒歩で6分程度。東京・南青山にある美術館です。
岡本太郎が1954年から亡くなる1996年までの42年間、住居兼アトリエとして使用してきた南青山のアトリエを改築したもの。2つの展示室で作品展示が行われるほか、多くの作品が生み出されてきたアトリエも、テーブルの上の道具や床に飛び散った絵の具なども生前の様子のまま見ることができます。

植物が生い茂る庭では、《河童像》や《母の塔》といったパブリックアートになった多くの彫刻作品たちがお出迎え。応接室には、岡本太郎のデザインした家具や食器などのマルチプル作品が並ぶのとともに、岡本太郎本人でシリコンの型取りをして制作されたというマネキンまで。

生前の岡本太郎のエネルギーを感じられるような空間です。
「東京国立近代美術館」は、皇居のほど近くに建つ国立の美術館で、13,000点を超える国内最大級の近代〜現代美術のコレクションを所有しています。

岡本太郎の作品としては、《コントルポアン》(1935/54)、《夜明け》(1948)、《燃える人》(1955)、《遊ぶ》(1961)、《反世界》(1964)の 5つの作品を所蔵。戦前に描かれた《コントルポアン》(1954年に再制作)は、「コントルポアン」という、違った旋律どうしを同時に組み合わせる作曲技法をモチーフにしたもの。戦火で焼失し、戦後に再制作された貴重な初期作品です。

これらの作品は、常設展示はされていませんが、所蔵作品展などで見ることができます。
続いて、「パブリックアート」作品や企業が公開している作品といった、いつでも誰でも見ることができる作品をご紹介します。

渋谷マークシティの連絡通路に設置された、高さ5.5M、幅30Mという、岡本太郎の作品の中でも最大スケールを誇る巨大壁画です。
メキシコ人実業家から建設中のホテルへの壁画を依頼され、1970年の大阪万博の《太陽の塔》の制作と並行して制作が進められた作品。しかし、1969年、作品の完成を目前にホテルの経営状況が悪化し、計画が頓挫。壁画は行方不明となっていました。
岡本太郎の没後、2003年にメキシコシティの資材置き場で発見され、修復された後、2006年に一般公開。2008年に現在の場所へ恒久設置されました。

「原爆」や「第五福竜丸」といった、日本にとっての重大な出来事をモチーフに、画面の中には、燃え上がる骸骨や不気味に広がるキノコ雲、燃えさかる人々などが描かれています。
太郎はこの作品について「原爆が爆発し、世界は混乱するが、人間はその災い、運命を乗り越え未来を切り開いていくー といった気持ちを表現した」と述べました。原爆を題材としながらも、その「悲劇」を描くのとは違ったエネルギッシュな作品です。
有楽町駅の近く、東急プラザ銀座隣の「数寄屋橋公園」のなかにある時計台です。「東京数寄屋橋ライオンズクラブ」と「銀座ライオンズクラブ」が「青少年の健全育成」を掲げた時計台を岡本太郎に依頼して制作されました。
岡本は銀座に足を運び、銀座の雑踏の中に静謐な作品を置いても埋没してしまうと考え、「周囲とまったく畏敬であり、異質でありながらピタリとあの場所に生きる、彩の濃い象徴」をつくることを決めたそう。
腕が四方八方に伸びる高さ約8Mのオブジェであり、夜は作品がライトアップされています。
岡本はこの作品について、「現代社会では狭い枠の中におさえられているが、しかし人間は本来八方に意欲を突き出し、情熱をほとばしらせて生きたいのだ。その若々しく、のびきった姿をここに打ち出した」と述べました。
東京・青山の国際連合大学本部の隣にある旧「こどもの城」前に設置されたオブジェ。「こどもの城」は、1985年に子どもの遊びを発信する国の施設としてオープン。およそ30年間で2800万人あまりが利用したものの、施設の老朽化などを理由に2015年に閉館していました。
高さ7.5M、幅5.3Mで、銀色の太い幹から、喜怒哀楽の表情が飛び出し、文化や人種も越えた無邪気な子どもの姿を表しています。
「子どもはみんな天才だ」といい、教育の現場に足を運ぶことや児童画展の審査も積極的に務め、自身でも児童画展を主催したという岡本太郎。この作品は、そんな岡本が子どもたちの個性と力を大切にするために作られたモニュメントです。
旧「こどもの城」は、2023年に「都民の城」としてリニューアルオープンを目指していたが、コロナ禍の影響で改修工事が開始できず断念。今後の動向が注目されています。
東京都府中市に位置する多磨霊園のなかにある、岡本太郎・敏子と、岡本の父・一平、母・かの子の墓標となっている彫刻作品です。
《顔》は、父・一平の墓であり、岡本がはじめて制作した立体作品。1952年に常滑の製陶工場に約1ヶ月間泊り込んだ際に花器として制作され、同年の草月展では、ストッキングや枯れ草などを生けて花器として出品されました。
一方、《若い夢》は、佐賀のかわでん工場内と、広島市現代美術館にも設置されているブロンズ彫刻。無邪気な子どもが頬杖をつくような作品です。1996年に岡本太郎が84歳で亡くなった際、養女でありパートナーである岡本敏子によって墓標に選ばれました。
岡本太郎
— 冨岡 準 (@jun_tomioka) December 28, 2019
『眼』『走る』『足』
於:国立代々木競技場第一体育館 pic.twitter.com/xLg5m3CqSe
1964年に開催された東京オリンピックのため、丹下健三の設計した国立代々木競技場第一・第二体育館に設置された陶製の壁画作品です。場所は、代々木公園の隣。
岡本太郎と丹下健三は、大阪万博のテーマ館や旧東京都庁舎など、多くの仕事を一緒に行ってきましたが、現在はこちらが建築と作品があわせて現存する唯一の場所となっています。
貴賓室入り口にある《プロファイル》は非公開、ほかの作品はイベント来場者のみに公開されます。
四谷で野生の岡本太郎を捕獲〜。『歓び』1978年。かつて四谷アートストゥディウムがあったお向かいです。 pic.twitter.com/AuNuwn1u2A
— ton yabumae (@ton0415) October 19, 2022
東京メトロの「四ツ谷駅」近くにある持田製薬本社前に設置されています。
岡本太郎と持田製薬二代目社長の持田信夫は親交があり、1970年の大阪万博の際には、太陽の塔の地下空間に展示された「DNAの二重螺旋構造」の制作は持田が無償で手がけてたそうです。
持田は、持田製薬創業65周年の記念として岡本に彫刻の制作を依頼。「歓びの心を持って、人々の健康的で豊かな暮らしに貢献したい」という持田の願いから《歓び》と名付けられました。
持田製薬本社ビルは立替が行われ、一時期作品も撤去されていましたが、2022年9月末から新オフィスビルとなり、再度公開されています。
「街の中の岡本太郎」作品紹介
— 岡本太郎美術館 動画制作中 (@okamotopr_SU) April 28, 2018
『太陽の神話』
樹と鳥の描かれた闇を二分するように、擬人化された太陽が中央で燦然と輝いています。
この様子は新しい世界の夜明けを意味しています。#太陽の神話#岡本太郎 #街の中の岡本太郎 #パブリックアート #モザイクアートを作ったろう pic.twitter.com/ySavoH75sP
東京駅にあるグランスタノウキョウノースタワー18F、大和証券グループ本社ビルのロビーに展示されています。伊奈製陶(現・INAX)が戦後まもなく発売した1センチ角のカラフルな小さなタイルを用い、岡本太郎が初めて手がけたモザイクタイル画です。モザイク壁画は1950年代後半〜70年代に流行しますが、岡本は早い段階でこの技術を取り入れました。
また、岡本の作品でおなじみの「太陽」のモチーフが顔と人格をもって立ち上がった初の作品でもあり、「新しい世界の夜明け」を意味していると言われています。

渋谷にあるNHK放送センターの中に展示された作品です。もともとは、NHKの物故職員を慰霊する多目的空間のために依頼されました。人々の鎮魂の意味を込め、男と女が7色に輝くオーラをまといながら天井の世界に昇天する姿がデザインされています。
1995年に放送局をリニューアルする際、設置されていた場所が「NHKスタジオパーク」のエントランスとなり、その場所にそのまま設置されていました。2022年現在、NHKスタジオパークは閉鎖され、壁画はNHKホールに移されて一般公開されているようです。
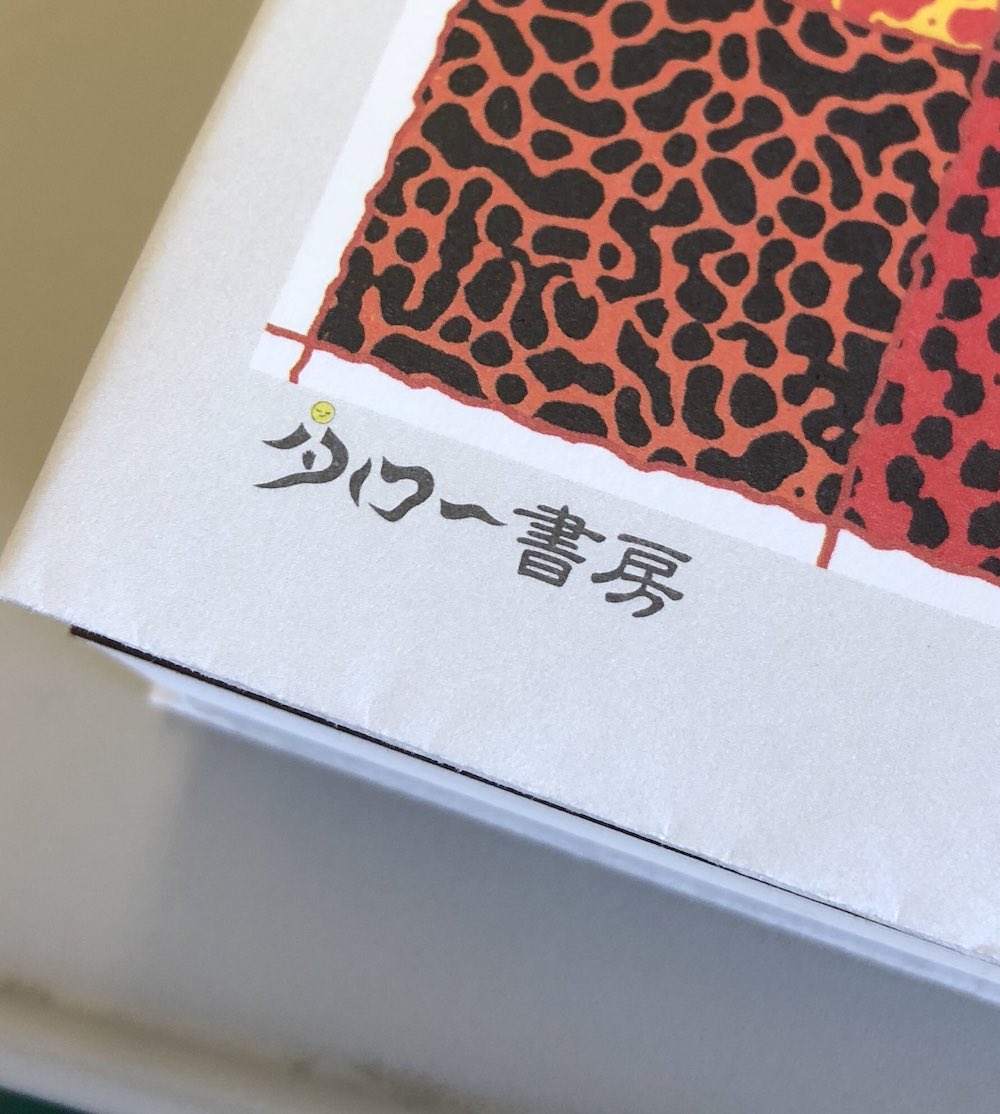
東京メトロ銀座線「三越前駅」の改札を出てすぐ、コレド室町の地下1Fにある書店。立体作品ではなく、こちらのロゴは、岡本太郎のデザインです。
タロー書房の初代社長が書店を開業する際に、看板用の文字を岡本に依頼したことによるものだそう。岡本太郎の特徴的な文字ですが、よく見ると、顔や足のようなモチーフも文字の中に取り入れられています。
看板に用いられているだけでなく、書籍を購入するとかけてもらえるブックカバーにもこのロゴがあしらわれており、岡本のデザインを持ち帰って楽しめます。(なお、店舗やブックカバーのデザインは、鉄道デザイナーの水戸岡鋭治が手がけています。)
美術館に収蔵された作品とは異なり、パブリックアートの作品は、設置していた建物の取り壊しなどを理由に失われてしまうものも。都内だけでも、現在は見ることができない作品が数多くありますが、その一部をご紹介します。
大森駅近くにあった、岡本太郎の手がけた唯一の建築物。「マミフラワーデザインスクール」の校舎として使用されていた建物です。「建築自身が彫刻であっても構わない」という思想で制作されたもので、青くピンと立った太い角のような柱が印象的です。
2002年に老朽化のために解体され、現在は新しい校舎が建てられています。
『日の壁、月の壁、赤、黄、緑、青』
— 岡本太郎美術館 動画制作中 (@okamotopr_SU) May 20, 2018
中央の吹き抜け壁には力強さを強調する《日の壁》そこから左に回り込んだ面には静謐を物語る《月の壁》を制作。
周囲の廊下や階段には「赤、黄、緑、青」の壁が色彩の効果を空間全体へと広げてる。
所在名称:旧東京都庁舎(現存せず)
#岡本太郎 pic.twitter.com/2j83NOnO2T
丹下健三が設計した旧東京都庁舎の壁面に展示されたレリーフ絵画。1956年、コンクリート打ちっぱなしのエントランスホールに物足りなさを感じた丹下健三が岡本太郎に相談を持ちかけて制作されたもので、合計11の壁画が設置されました。
1959年には丹下健三とともにフランスの建築雑誌「今日の建築」から「国際建築界が大賞」を受けるなど、国際的な評価も高い作品です。

1991年の都庁移転に伴い解体。当時、壁画を保存すべく「太郎壁画なんとかならない会」も結成されたものの、岡本太郎自身は「仕方ないね」と無頓着だったというエピソードも。
取り壊しに際し、都は11作品のうち、特に代表的な《日の壁》《月の壁》の1/5レプリカを岡本に依頼し、東京都現代美術館に所蔵されています。
「街の中の岡本太郎」作品紹介
— 岡本太郎美術館 動画制作中 (@okamotopr_SU) April 30, 2018
『創生』
壁面に恒久設置される壁画として初めての作品です。
人と樹の融合体が枝を広げコミカルな表情をした恐竜と雲の親子が描き「合理性」に対する「不合理」を表現してます。#創生#岡本太郎 #パブリックアート #モザイクアートを作ったろう pic.twitter.com/UI7BFO0xpi
岡本太郎がはじめて公共空間につくった壁画の代表作です。東京日本橋・高島屋の地下通路につくられたもので、坂倉準三建築とのコラボレーションとなりました。
人と樹が融合した生きものが手を広げ、その左右で恐竜と雲の親子が躍動感を生み出しており、坂倉準三の目指す「近代」と逆行する「太古」のイメージがつくりだされています。
メリーポール初公開!
— 岡本太郎記念館 (@taro_kinenkan) June 6, 2018
1962年、太郎が制作し池袋に設置されたメリーポール。
当時の模型が修復され、美しく妖しいフォルムが出現しました。
企画展「太陽の塔への道」は、呪術的な気配に満ちた60年代の作品を俯瞰しながら、万博前夜の太郎を体感します。 pic.twitter.com/DwPZM6MrQY
1962年に東京・池袋のイメージアップを狙って制作を依頼されたクリスマスツリー。
色とりどりのライトが仕込まれ、夜には美しい光のオブジェとなるものだったそうです。1962年のクリスマス時期に点灯されましたが、その後撤去されています。

都内だけでも多くの場所で岡本太郎の作品を見ることができます。ただ、パブリックアートは周囲の環境の変化の影響も大きく受け、すでに失われてしまった作品も多いです。
都内に現存している作品でも、公開が中止となっていたり、今後の存続が危ぶまれている作品も。是非、みられるうちに訪問してみてくださいね。